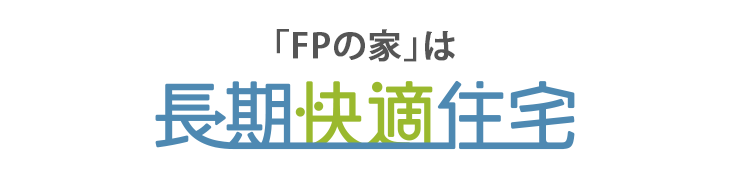「炭の家」に使われる岩手県産の炭。製造工程を見てきました!
2021年3月4日 ブログこんにちは!スタッフのマダです。
すっかりご無沙汰のブログですが・・・
これを機会に、気が向いたら書き込んでいこうと思います。
よろしくお願いいたします!
さて、去る2月19日、
サトコンの新人スタッフとそうでないスタッフ
(私もかれこれ6年おりますが、知識も経験もベテランとは言えない…)で
岩手県久慈市の炭焼き小屋、枝成沢林業土木さんにお邪魔してきました。
サトコンスタッフとしてはもちろんですが、
実際に「炭の家」住む人間としても、炭が気になるところ。
しっかりと学んできました。
実は、折角なので、炭次郎さんになってみたのですが、
眼鏡をかけた40代の私は、野沢雅子先生にしか見えず(T▽T)アハハ!
なんて車の中で笑っていたら、炭焼き小屋の作業員さんにも
「炭次郎?野沢雅子に見える!」と(ノ∀`)σ
笑いを取れて良かった~!(そこ??)
まずは90㎝にカットされた木を

巻き割り機で割っていきます。

ある程度同じ太さになるように薪を割ったら、

窯に並べていき、入口をふさぎます。

塞ぐためのブロックの隙間は、
窯を作る土と炭焼きの際に発生した炭を
混ぜたもので埋められます。

いよいよ火を入れて、(あ、私はフリだけです)

グツグツコトコト・・・ヘ(。。ヘ)☆パシッヽ(^^;)

ではなく、1週間かけて窯内の温度を500℃まで上げて、
そのあとは通気口をすべて防ぎ、
さらに1週間かけて窯内の温度を60℃まで下げます。
そこから炭を出して選別され、
いいものは6㎝にカットして箱に詰めて出荷されます。

その時にはじかれた炭も、発生する粉末も、
様々なところですべて利用されるそうです。
また、窯は休ませてしまうと温度が下がるため、
常に作り続けているとのこと。
手間暇をかけて作られた炭を、皆様のおうちに設置させていただく
私たちも責任重大だなと思いました。
地産地消の炭。
それを贅沢に使って空気をキレイにできるなんて、
見えないけれど幸せですね♪
-
お問い合わせ
家づくりに関するお問い合わせは
お電話またはお問い合わせフォームから